固定(みなし)残業
固定残業代とは?
固定残業代とは、基本給の一部や残業手当(その他名目を問わず時間外労働への対価として支払われる手当)を定額(固定)で支給する方法によって支払われる時間外労働への割増賃金のことです。要するに、何時間分の残業代としてこの金額(定額)を払いますよ!という趣旨の手当のことです。

固定残業代制度は有効?
このような残業代の支払い方は、固定残業代を超える時間残業した場合には当然超えた部分は追加的に残業代請求できる一方で、固定残業代に満たない時間しか残業していない場合でもその固定金額を労働者が受け取れるという意味において労働者にとって有利であり、使用者にとっても残業代計算の管理が簡単になるため、有効なものと理解されています。
ただし、固定残業代制度が有効であるためには、基本給部分と残業代の部分は明確に区分されている必要があります(最判昭63.7.14 小里機材事件)。

< 固定残業代制度が有効であるといえるためには >
- 基本給と割増賃金部分が明確に区分できること(契約書、就業規則、給与明細等の記載を確認)
- 割増賃金部分とされている賃金(手当)の額が、労基法の定める賃金額を下回っていないこと
上記は、必須の要件とされます(①につき最判平24.3.8 テックジャパン事件等、②につき最判平29.2.28 国際自動車事件等)。
< 固定残業代制度の種類 >
固定残業代制度を採用する、少なくともそのように主張する会社はたくさんありますが、固定残業代制度は大きく分けると、基本給に組み込んで支払う組込型と各種手当を残業代として支払う手当型に分かれます。
固定残業代が有効か無効かでは、単に支払った金額が残業代になるのかならないのかという問題に留まらず、残業代の基礎となる基本給に組み込まれるかどうかにも直結します。このように二重の意味で未払い残業代計算に影響することから、固定残業代制度の有効性は頻繁に重要な争点となります。
< 固定残業代制度の有効・無効の具体的判断基準は? >
固定残業代制度が有効であるためには、基本給部分と残業代部分が明確に区分されている必要があります。そのため、一般論としては、組込型と手当型では手当型の方が明確区分性の要件を満たしやすいといえます。ただし、もちろん組込型で有効であると判断される場合もあれば手当型で無効と判断される場合もあり、個別具体的に判断するよりありません。
< 明確区分性はどこまで要求されるか? >
明確に区分されていることといっても、基本給のうち何時間分は残業代と明示されていれば良いのかというと、そういうわけではありません(東京地判平21.1.30 ニュース証券事件等)。逆に、基本給のうち○円部分は、○時間分の時間外労働割増賃金として支払うということが明示されていれば、明確区分性は充足されていると判断される可能性が高いでしょう。
他方で、手当型の場合に、何時間分の割増賃金として支払うかを明示する必要もないとする裁判例もあります(東京高判平27.12.24 富士運輸(割増賃金)控訴事件)。
明確区分性がどこまで要求されるかについては、裁判例でも少し錯綜していた感がありますが、最高裁第一小法廷平成30年7月19日判決(日本ケミカル事件)以降の裁判例では、金額と時間が明確になっており割増賃金の趣旨で払われていれば、固定残業代としての支払いを有効として認める傾向にあるように思われます。
なお、明確区分性が必要であるとしたテックジャパン事件(最判平24.3.8)の枠組みを変更するものではなく、これに付加的に上記の枠組みが示されたと考えるべきでしょう。
〜 ミニコラム 〜
日本ケミカル事件(最判平30.7.19)原審の判断との違い
日本ケミカル事件は、薬剤師としてYに雇用されたXが、固定残業代として支払われていた業務手当は残業代の支払いとしては無効であると主張して時間外労働及び深夜労働の割増賃金の支払いを求めた事件です。
原審(東京高判平29.2.1)では、「定額残業代を上回る金額の時間外手当が法律上発生した場合にその事実を労働者が認識して直ちに支払を請求することができる仕組み(発生していない場合にはそのことを労働者が認識することができる仕組み)が備わっており、これらの仕組みが雇用主により誠実に実行されているほか、基本給と定額残業代の金額のバランスが適切であり、その他法定の時間外手当の不払や長時間労働による健康状態の悪化など労働者の福祉を損なう出来事の温床となる要因がない場合に限られる」と、かなり厳格な要件を示しました。これは、使用者側にとっては相当きつい要件でした。
しかし、この点について最高裁は、「原審が判示するような事情が認められることを必須のものとしているとは解されない」と原審の判断を一蹴し、「ある手当が時間外労働等に対する対価として支払われるものとされているか否かは、雇用契約に係る契約書等の記載内容のほか、具体的事案に応じ、使用者の労働者に対する当該手当や割増賃金に関する説明の内容、労働者の実際の労働時間等の勤務状況などの事情を考慮して判断すべき」と判示しました。
この最高裁の判断は、従前の明確区分性の要件に直接は触れていないものの、本件では明確区分性は十分に満たされていることを前提に、「時間外労働等に対する対価として支払われるものとされているか否か」ということの判断についての枠組みを示したものと考えられます。
固定残業代として認められる残業時間の上限
固定残業代として、45時間を超える時間分の割増賃金を支払う契約が有効かという問題があります。労働基準法上、原則として残業は月45時間が上限とされているからです。その他、年720時間まで、2ヶ月以上の複数月平均80時間以内、月100時間未満という規制もあります。
こうなると、そもそも法律違反となるような残業時間を前提とする固定残業代制度を有効にして良いのかという話になるわけです。
この点に関する裁判例として、月95時間分の時間外賃金として職務手当が支払われていた事案で、月45時間分の対価として合意がされているものと認めたもの(札幌高判平24.10.19 ザ・ウィンザー・ホテルズインターナショナル事件)、同様に月100時間分の時間外手当として支払われていた営業手当位について当該営業手当が割増賃金とは認められないとしたもの(東京高判平26.11.26 マーケティングインフォメーションコミュニティ事件)、同様に月83時間分の残業代として規定されていたものを無効としたもの(岐阜地判平27.10.22 穂波事件)、月50時間分の時間外手当として営業手当が支払われていたがその手当の額が実際の労基法の定めに従った計算より下回っていたことから無効としたもの(東京地判平26.8.20 ワークスアプリケーションズ事件)などがある一方、業務手当が月70時間の時間外労働と100時間の深夜労働の対価として支給されていたが、会社が36協定において月45時間を超える特別条項を定めていることから、違法とは認められないとしたもの(東京高判平28.1.27 X社事件)もあります。
私見としては、月45時間を超える前提の固定残業代制が直ちに無効になるとは思われないものの、それまで大臣告示によって定められていた月45時間という残業時間上限は、2019年の労働基準法改正で罰則付の上限として設定された経緯や、改正内容として年720時間以上の残業も禁止されたことなどからすると、少なくとも月60時間を超える固定残業代制度は、労働基準法の定めに反し無効となる可能性が高いのではないかと思われます。
Webからのお問い合わせの方は、
下記お問い合わせボタンからご連絡下さい。

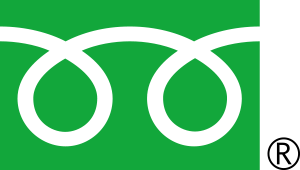 0120-659-523
0120-659-523